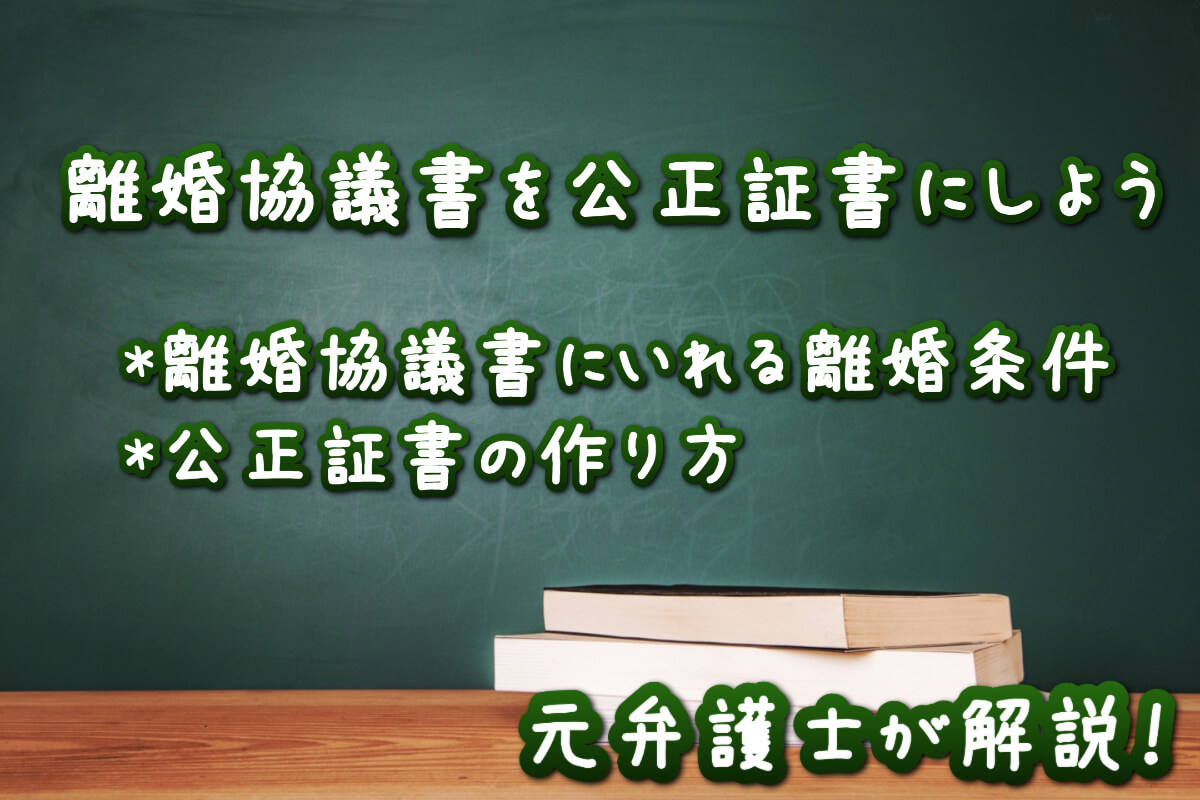
夫婦が協議離婚で別れるときには「離婚協議書」を作成すべきですが、それだけでは足りず「公正証書」にしておくのが望ましいです。
どうして公正証書にしておくべきなのでしょうか?
また公正証書を作成したいとき、どのような手続きをとればよいのかわからないという方もおられます。
今回は離婚協議書の公正証書を作成する意味と記載すべき内容、自分たちで公正証書を作成する方法をご紹介します。
離婚協議書とは

協議離婚をするときには「離婚協議書」を公正証書化して「離婚公正証書」を作成しておくべきです。
このように「離婚公正証書」は「離婚協議書」にもとづくものですから、まずは「離婚協議書」がどのようなものか、簡単に確認しておきましょう。
離婚協議書は夫婦の契約書
離婚協議書とは、夫婦が協議離婚をするときの離婚条件を書面にまとめたものです。
慰謝料や財産分与、親権や養育費などの事項が細かく条項化されていて、契約書のようになっています。
本文を書いて夫婦それぞれが署名押印をして、日付を書き入れると有効になります。
離婚協議書を作成する目的
離婚協議書を作成するのは、夫婦が協議離婚の話合いで合意した内容を明らかにするためです。
確かに協議離婚をするときには、子どもの親権者以外の事項を決める必要がありません。
しかし慰謝料や財産分与などのその他の離婚条件についても取り決めをしておかないと、離婚後のトラブルにつながります。
たとえば財産分与について取り決めをしていなかったら、離婚後相手に対して財産分与請求をしなければなりません。
相手が拒絶したら、家庭裁判所での財産分与調停が必要となります。
旦那さんや奧さんが浮気したせいで離婚したのであれば、離婚時に慰謝料の支払いについて約束していないと、離婚後に元配偶者や浮気相手などに慰謝料請求の裁判を起こさなければならないケースもあります。
そのようなトラブルを避けるため、離婚協議書を作成しておきます。
口約束だと、相手が後になって「そんな約束をしていない」と言う可能性があるので、相手にもきっちり署名押印させて書面化しておく必要があるのです。
公正証書とは

それでは、離婚協議書を「公正証書化」するときの「公正証書」とは何なのでしょうか?
公正証書は「公証人」という人が作成する公文書です。
公証人は、公正証書作成を専門的に行っている公務員です。
公正証書は公証人が法律の定める手続きに従って作成するもので、できあがったら原本が「公証役場」で保管されます。
契約の当事者には「正本」や「謄本」という「写し(コピー)」が交付されます。
契約書類であれば、だいたいどのようなものでも「公正証書」にできます。
たとえば借金するときの「金銭消費貸借契約書」や不動産を借りるときの「賃貸借契約書」、ビジネスの場面における「取引基本契約書」や「業務委託契約書」「株式売買契約書」「出資契約書」なども公正証書化ができます。
また遺言書も公正証書で作成できます。
遺言書を公正証書化した遺言公正証書は非常に信用性が高く無効になりにくいので、広く利用されています。
「離婚協議書」も夫婦が離婚するときの契約書の1種なので、公正証書にできます。
離婚協議書を公正証書にしたものを「離婚公正証書」といいます。
離婚協議書を公正証書にする意味

離婚後のトラブルを避けるためには、夫婦で話し合って離婚条件を取り決めて、自主的に離婚協議書を作成したらそれだけで充分なようにも思えます。
それ以上に、どうして公正証書にする必要があるのでしょうか?
相手から「偽造」と言われない
1つには離婚公正証書にしておくと、相手から「偽造」と言われにくいメリットがあります。
夫婦が自分たちで離婚協議書を作成しただけの場合、相手から「そんな合意書は作成していない」「妻が勝手に署名押印を偽造したもので、無効だ」などと言われる可能性があります。
また「妻の親族に取り囲まれて無理矢理署名押印させられたので、取り消す」などと言われるケースもあります。
そうなったら離婚協議書が無効になって、せっかく取り決めをした意味もなくなってしまいます。
離婚公正証書にしておけば、公正証書作成の際に公証人が当事者双方の意思を確認した上で、公証人の目の前で本人に署名押印をさせます。
後になって本人が「そんな約束をしていない」「勝手に署名押印を偽造された」とは言えなくなります。
また公証役場で公正証書を作成するのですから「脅迫されて無理矢理署名押印させられた」という主張も通りません。
無効にならない
公正証書にすると、離婚協議書が無効になりにくいメリットがあります。
自分たちで書面を作成すると、どうしてもいろいろな不備が発生してしまうリスクがあります。
たとえば署名押印を忘れてしまったり、法律的な表現がわからないので文言内容が不正確になってしまったり、無効な取り決めをしてしまったり余計な内容を書いてしまったりする例がみられます。
せっかく離婚協議書を作成しても、内容に不備があって無効になったら意味がありません。
離婚公正証書なら公証人が職務として法律によって定められた方法で作成するので、不備によって無効になる可能性はありません。
紛失のおそれがない
公正証書は紛失のおそれがない点も大きなメリットです。
公正証書が作成されると原本が公証役場で保管されるからです。
当事者に交付されるのは「正本」「謄本」という写しだけなので、なくしてしまっても何度でも謄本申請できます。
これに対し、もしも自分たちで離婚協議書を作成しただけであれば、なくしてしまったらもう一度作成するのは難しくなります。
離婚協議書の紛失後、相手から「そんな約束はしていない」と言われるとそれ以上の慰謝料や養育費の請求ができなくなってしまうでしょう。
強制執行ができる
離婚公正証書を作成すると、相手が約束通りの支払いをしないときに「強制執行」ができます。
たとえば養育費や財産分与、慰謝料などの支払を約束しても、相手が約束通りに支払いをしてくれないケースがあります。
その場合、単なる離婚協議書しかなかったら相手に支払いを要求しなければなりませんし、それでも支払ってもらえなかったら養育費調停や財産分与調停、慰謝料請求訴訟などをしなければなりません。
最終的に支払いを受けられるまでに、何か月もかかってしまいます。
もしも離婚公正証書を作成して「強制執行認諾条項」を入れておけば、相手が不払いを起こしたときにすぐに差押えができます。
調停や裁判のステップを飛ばせるのです。手間もかかりませんし、早期に確実に支払いを確保できます。
そこで、特に財産分与や慰謝料を分割払いにするケースや養育費を支払ってもらう場合などには、離婚公正証書を作成する意味が大きくなります。
支払い期間が長くなると、どうしても不払いのリスクが高くなるからです。
旦那さんや奧さんが浮気して、離婚後に浮気の慰謝料を分割払いしてもらう場合や、子どもを引き取って相手から養育費を支払ってもらう場合などには、必ず「離婚公正証書」を作成しておきましょう。
公正証書が必要なのは「協議離婚」のケースのみ

ところで離婚の手続きには協議離婚と調停離婚、審判離婚、裁判離婚(判決離婚、和解離婚、認諾離婚)がありますが、この中で「離婚公正証書」が必要なのは「協議離婚」だけです。
調停や審判、裁判で離婚する場合には、離婚公正証書作成の必要がありません。
調停や審判、裁判で離婚すると、裁判所で調停調書や判決書、和解調書や認諾調書という書類が作成されます。
これらの書類は裁判所で保管され続けますし、裁判官や書記官が作成するので偽造のおそれや無効のリスクもありません。
また裁判所の作成する書類にも、公正証書と同様「強制執行力」が認められるので、わざわざ公正証書にする必要もないのです。
むしろ裁判所の書類の方が公正証書よりも効力が強いです。
調停や審判、裁判で離婚する場合には、相手が不払いを起こしたとき、裁判所から受け取った書類をもとに相手の給料や預貯金等を差し押さえられます。
公正証書を作成する方法

次に公正証書を作成する具体的な流れや方法をご紹介します。
公正証書を作成する流れ
公正証書を作成するときの流れは、以下の通りです。
- まずは自分たちで離婚条件を決める
- 離婚協議書を作成する
- 公証役場に申込みをする
- 必要書類を用意する
- 当日相手と一緒に公証役場に行く
それぞれのステップについてみていきましょう。
まずは自分たちで離婚条件を決める
離婚公正証書を作成するとき、事前に夫婦が自分たちで話合いをして希望する離婚条件を決めておかなければなりません。
公証役場に行けば公証人が相談に乗ってくれますが、それは「公正証書の作成方法」についての相談であり「離婚条件の決め方」についての相談ではないからです。
離婚条件や法律問題についての正しい考え方や意見を求めたい場合には、弁護士に相談する必要があります。
話合いで決めるべき離婚条件は、以下のような事項です。ここで決めた内容が公正証書に記載されます。
財産分与
夫婦の共有財産があれば、財産分与の方法について取り決めましょう。
たとえば夫婦の名義の預貯金や生命保険、不動産や車、退職時期が近い場合には退職金も財産分与の対象になります。
子ども名義の預貯金や学資保険なども財産分与の対象になるので注意が必要です。
財産分与の割合は基本的に夫婦が2分の1ずつとなりますが、話合いで財産分与方法を決めるときには必ずしも2分の1ずつにする必要がありません。
旦那さんが浮気して離婚になった場合などには、奧さまが慰謝料代わりにすべての財産を分与してもらうケースなどもあります。
また財産分与の「支払い方法」まできっちり取り決めておく必要があります。
一括払いにするならいつまでに支払うのか、分割払いならいつからいつまでいくらずつ支払うのか、毎月払いにするなら何日払いにするのか、入金先の銀行口座まで正確に特定しましょう。
慰謝料
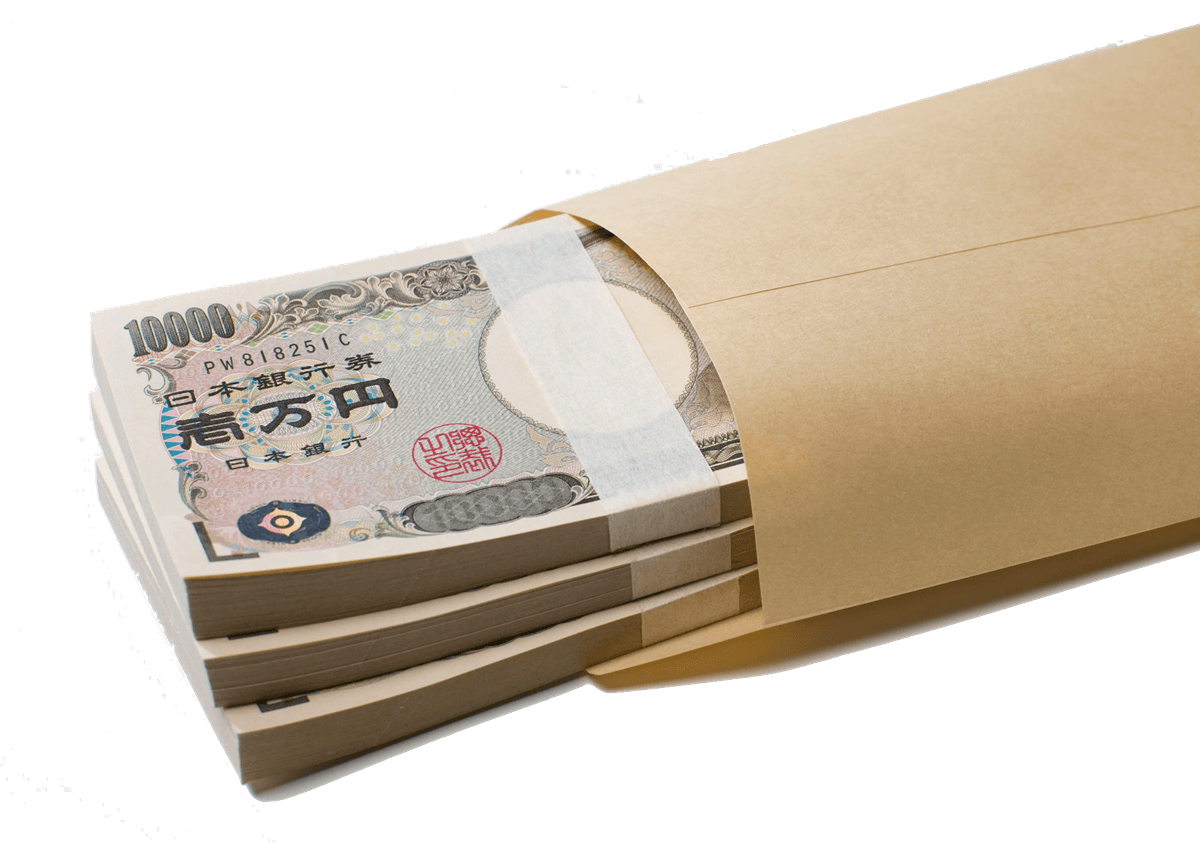
相手が浮気して離婚する場合などで慰謝料請求をするなら、慰謝料についても決めなければなりません。
まずはいくらの慰謝料を払ってもらうのかを決める必要があります。金額については、慰謝料の相場を参考にして決めると良いでしょう。
浮気の慰謝料の相場については、以下の記事で詳しく説明しているので、ご参照下さい。
-

-
浮気の慰謝料相場はどのくらい?ケースごとの金額と高額にする方法について
信じていた夫や妻が浮気していると分かったら、とてもショックですし「許せない」と感じるでしょう。 そのようなとき「浮気の慰謝料」を請求できますが、慰謝料の金額はどのくらいになるのでしょうか ...
また慰謝料についても支払い方法が問題です。
一括で支払えない場合には分割払いも検討する必要があります。支払い期間や入金期日など、具体的に取り決めておきましょう。
親権
未成年の子供がいる場合には、必ず親権者を決めなければなりません。
子どもの親権者が決まらないと協議離婚できませんし、親権者についも離婚公正証書に書き込む必要があるからです。
養育費
子どもがいる場合、養育費の金額の取り決めも必要です。
養育費を定めておかないと、離婚後に「養育費調停」をしないと支払ってもらえなくいケースが多数ですし、調停の手続きが面倒で諦めてしまう方もおられるからです。
離婚公正証書によって養育費の取り決めをしておくと、相手が支払いをしてくれないときにすぐに「差押」ができますが、養育費にもとづいて差し押さえをするときには、相手の給料の手取り額の2分の1まで押さえられます。
その他の通常の債権の場合には4分の1が限度ですので、養育費は通常より優遇されています。
またいったん給料を差し押さえると、毎月の給料やボーナスから自動的に養育費を支払ってもらえるので、養育費を確実に回収しやすくなります。
養育費の金額は、家庭裁判所の定める養育費算定表(http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)に従って決めると良いでしょう。
面会交流
子どもとの面会交流についても公正証書によって定められます。
ただし面会交流は金銭債権ではないので、相手が守らなかったとしても「強制執行」によって実現するのは不可能です。
ただ公正証書化によって面会交流の権利と義務、実施方法がはっきりしますし、取り決めた証拠が残るので相手にプレッシャーを与えられて、面会交流を実現できる可能性が高くなります。
年金分割
旦那さまや奥さまが厚生年金や共済年金に加入している場合には「年金分割」を利用できます。
年金分割とは、夫婦が婚姻中に払い込んだ年金保険料を分け合う手続きです。
配偶者の一方が「3号被保険者」で婚姻したのが平成20年4月以降であれば、特に合意をしなくても0.5(2分の1)の年金分割を受けられますが、それ以外のケースで年金分割をするには夫婦が年金分割に合意して分割割合も決めておかなければなりません。
「3号被保険者」とは旦那さまに扶養されている妻などですが、3号被保険者であっても平成20年3月以前から婚姻している場合、年金分割には旦那さまの合意が必要です。
公正証書で年金分割を取り決めておけば、年金分割を受ける側の配偶者が1人で年金事務所に行って年金分割の手続きができるので、楽です。
もしも公正証書がなかったら、離婚後旦那さんと妻が一緒に年金事務所に行って「標準報酬改定請求書」という書類を提出して年金分割の申請をしなければなりません。
合意分割の年金分割割合は夫婦が話合いによって0.5までの割合で自由に定められますが、裁判所で調停をした場合などにはほとんど必ず0.5となります。そこで自分たちで話合いをするときにも0.5にしておくのが公平です。
離婚協議書を作成する
上記のような公正証書に記載する離婚条件についての取り決めができたら、自分たちで簡単な離婚協議書を作成しましょう。
このとき相手も公正証書にするという同意をしているなら、あとは公証役場に行って説明すれば手続きができるので、詳細な離婚協議書までは不要だとも考えられます。
しかし、離婚公正証書が完成するまでの間に相手の考えが変わってしまう可能性もあります。
その場合離婚協議書を作成していなかったら、せっかく話し合って取り決めた内容がすべて無駄になってしまいます。
そこで相手と話合いをして合意ができたら、できるだけその時点で離婚協議書を作成し、日付を入れて夫婦双方が署名押印して書面を完成させておきましょう。
公証役場に申込みをする

離婚協議書が完成したら、それをもって公証役場に行き「離婚公正証書作成」の申込みをしましょう。
公証役場は全国各地にあり、どこの公証役場を利用してもかまいません。
こちらのサイトから利用しやすい公証役場を探して連絡しましょう。
-
-
公証役場一覧 | 日本公証人連合会
全国各地の公証役場のご紹介です。日本公証人連合会。
続きを見る
公証役場に行って事前に作成しておいた離婚協議書を渡すと、公証人が離婚公正証書の作成について検討してくれます。
公正証書にできない部分があったりもう少し特定が必要なところがあったりすると、具体的に指摘を受けられます。
公正証書化できない部分があればその部分を省略して離婚公正証書を作成してもらいますし、さらに特定が必要な部分があれば再度旦那さんや奧さんと話合いをして詳細事項を決めてから離婚公正証書を作成してもらいます。
詳細な離婚協議書を作成しておらず、簡単なメモを持って行くだけでも意味がわかれば離婚公正証書を作成してもらえます。
自分たちで離婚協議書まで作成するのが大変だという場合には、とりあえず希望する条件をまとめて公証役場に相談に行くと良いでしょう。
必要書類を用意する
公証役場で離婚公正証書を作成すると決まったら、公証人から必要書類を集めるように指示されます。離婚公正証書を作成するためには、最低限以下の書類が必要です。
- 戸籍謄本
- 夫婦の身分証明書(運転免許証やパスポートなど)
- 印鑑登録証明書
- 実印
財産分与を行う場合には、財産を示す資料も必要となります。
たとえば以下のようなものです。
- 不動産の全部事項証明書
- 不動産の固定資産評価証明書
- 預貯金通帳、取引明細、残高証明書等
- 生命保険証書
- 株式や投資信託の明細書
具体的には担当の公証人に相談して、指示された通りの書類を持参しましょう。
書類が欠けていると、せっかく公証役場に行っても離婚公正証書を作成してもらえない可能性があるので、指示されたものは確実に集める必要があります。
当日相手と一緒に公証役場に行く
必要書類が揃ったら、指定された日時に配偶者と一緒に公証役場に行きます。
公証役場では既に離婚公正証書ができあがっているので、公証人から読み聞かせてもらって、内容に間違いがなかったら夫婦がそれぞれ署名押印します。
そして公証人も署名押印して日付を入れると離婚公正証書が完成します。
離婚公正証書ができあがったら原本は公証役場に保管されますが、当事者には「正本」または「謄本」が交付されます。
写しをなくしてしまった場合には「謄本申請」をすれば、費用を払っていつでも「謄本」をもらえます。謄本の交付費用は公正証書1枚につき250円です。
離婚公正証書を作成するときの注意点

次に離婚公正証書を作成するときの注意点をご説明します。
離婚公正証書の作成料金
離婚公正証書を作成するためには費用がかかります。
具体的には目的とする金額によって異なります。
たとえば相手に請求する慰謝料や財産分与の金額が大きくなると、離婚公正証書にかかる費用が高額になります。
目的物の金額と手数料の関係は以下の通りです。
| 目的物の金額 | 手数料 |
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 200万円以下 | 7,000円 |
| 500万円以下 | 11,000円 |
| 1,000万円以下 | 17,000円 |
| 3,000万円以下 | 23,000円 |
| 5,000万円以下 | 29,000円 |
| 1億円以下 | 43,000円 |
| 1億円を超えて3億円以下 | 5000万円ごとに13,000円を加算 |
| 3億円を超えて10億円以下 | 5000万円までごとに11,000円を加算 |
| 10億円を超える | 5000万円までごとに8,000円を加算 |
また離婚公正証書が4枚を超える場合、1枚ごとに250円が必要です。
相手方(債務者)に対して謄本を送達するための送達手数料として1,400円、送達のための郵便代実費として1,110円~1,240円が必要です。
送達証明書をもらいたいときには、送達証明書の手数料が250円必要となります。
「送達」は相手が約束通りに支払いをせず差し押さえをするときに必要な手続きです。
滞納されてから送達してもかまわないのですが、そのときに送達すると相手が差押を警戒して財産を隠したり仕事を辞めてしまったりする可能性があるので、公正証書を作成したときに先に送達しておいてもらうのが良いでしょう。
また年金分割をするときには別途手数料が11,000円必要です。
このように離婚公正証書を作成するときにはある程度費用がかかります。最低でも5,000円かかりますし、多くのケースでは数万円が必要となるでしょう。
そうなると夫婦のどちらが支払うべきか問題となります。
この場合夫婦がそれぞれ半額ずつ負担するのが公平ですが、公正証書を作成したいと希望するのは「支払いを受ける側(債権者)」であるケースが多いです。
債務者にしてみると「なぜ差押を受ける可能性のある書類を作成するのに、自分がお金を払わないといけないのか」という気持ちになります。
「お金を支払わなければならないなら、公正証書作成に協力しない」と言い出すケースもあります。
養育費などの支払いを確実に受けるためには、相手が「費用を負担するなら公正証書を作成しない」という態度をとる場合、自分が費用を全額負担してでも離婚公正証書を作成しておいた方が良いケースがあります。
相手が公証役場に来られない場合
離婚公正証書を作成するときには原則的に夫婦二人が双方とも公証役場に出向く必要がありますが、相手によっては「来たくない」ケースがあります。
忙しくて日程を調整できない場合もあるでしょう。
相手が公証役場に来られない場合には、公証人に出張してきてもらうか代理人を立てる方法があります。
出張してもらった場合には4時間までであれば1万円、1日であれば2万円の日当と交通費が必要です。
代理人を立てる場合には本人から代理人へ委任状を渡して、本人確認書類や印鑑登録証明書などの書類を提示すれば代理人による署名押印によって公正証書を作成できます。
浮気相手への浮気慰謝料については記載できない

離婚公正証書は浮気相手との契約ではない
旦那さんや奧さんの浮気が原因で離婚する場合、浮気相手に対しても慰謝料請求をしたいと考えるケースがあります。
ただ旦那さまや奥さまとの「離婚公正証書」によって、浮気相手に対する慰謝料請求の取り決めはできません。
離婚公正証書はあくまで旦那さまや奥さまとの約束事であり、浮気相手との契約ではないからです。
浮気相手への請求を公正証書にする方法
浮気相手に対する慰謝料請求を公正証書にしたい場合には、浮気相手と話し合って合意をしなければなりません。
まずは浮気相手と慰謝料支払いについて取り決めをして、公正証書作成についても納得させます。
そして公証役場に申込み、あらかじめ取り決めておいた慰謝料の金額や支払い条件を公証人に伝えると「浮気の慰謝料支払いに関する合意書(公正証書)」を作成できます。
この場合には浮気相手本人に公証役場に来てもらって、署名押印をさせなければなりません。
公正証書作成費用がかかるので、浮気相手が支払いを拒む場合には債権者が負担しなければならない可能性もあります。
このようにして浮気相手との慰謝料支払いについての公正証書ができれば、その後浮気相手が慰謝料を支払わなくなったとき、浮気相手自身の預貯金や生命保険、給料などを差し押さえる方法が可能となります。
自分が支払う側である場合の問題点!公正証書作成に応じるべきか

公正証書を作成すると、債務者が支払いをしなかったときにすぐに財産や給料を差し押さえられるので、支払う債務者側にとっては大きな負担となります。
たとえば自分が養育費や財産分与を支払う場合「公正証書を作成して良いのか?」と疑問を持つ方もおられます。
協議離婚をするとしても、必ず離婚公正証書を作成しなければならないというものではありません。
公正証書を作成しないで離婚届を提出して終わっている夫婦もたくさんいます。
そこで相手から公正証書作成を求められたとき、拒絶するのも1つの方法です。
しかし相手がどうしても強制執行力のついた書面がほしいという場合、公正証書作成を断ると離婚調停を申し立てられる可能性があります。
どうせ調停で同じ条件で離婚するのであれば、協議離婚しておいた方が手間も時間もかかりません。
離婚条件自身に不服がなく、相手が公正証書の費用を出すと言っているならば、離婚公正証書の作成に応じた方が良いケースが多いでしょう。
公正証書で無理な約束をしない
いったん離婚公正証書を作成してしまったら、債務者が約束を破ったときには給料や資産を差し押さえられるので、債権者にとってメリットがあるように思えます。
しかし「無理な約束」をさせてしまうと、債権者にも不利益が及ぶ可能性があるので注意が必要です。
たとえば相手が慰謝料と財産分与と養育費を支払う場合、離婚後には毎月その3つの合計の費用負担が発生します。
このとき相手が支払える範囲にしておかないと、結局不払いが起こって債権者に迷惑がかかります。
強制執行すれば良いと思うかも知れませんが、強制執行をしても相手が「請求異議」や「仮処分」の手続きをとると、強制執行が中止される可能性があります。
差し押さえをするためには、その裁判を進めて勝訴しなければならないのです。
また養育費減額調停を、同時に起こされる可能性も高いです。
そうなると、裁判や調停への対応が必要となり、法律関係がめちゃくちゃに複雑になってしまいます。
ストレスも無駄な時間も労力も費用もかかります。
このように支払いができない約束をするとお互いが不幸になるだけなので、いかに相手に迷惑をかけられた事案であっても支払金額を「相手が支払える現実的な金額」に設定しておく方が良いのです。
まとめ
協議離婚をするときには、離婚協議書を作成して離婚公正証書にしておくと、離婚後のさまざまなトラブルを避けやすくなります。
特に自分が慰謝料や養育費などの支払いを受けるのであれば、必ず離婚公正証書を作成しておきましょう。
まずは相手と話し合いを進めて公証役場に申し込むと良いです。自分たちだけでは不安な場合には弁護士に相談するのも良いでしょう。
-
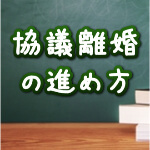
-
協議離婚の進め方!有利に進めるポイントを解説
夫婦が離婚するときには「協議離婚」の方法で離婚するケースが圧倒的に多数です。 協議離婚するときにはどのような流れになるのか、また協議離婚で有利に離婚するためにはどのような点に気をつけたら ...
-

-
離婚届の正しい書き方と提出方法、作成の注意点について
旦那さまや奥さまと離婚すると決めたら「協議離婚」するケースが圧倒的に多いです。 そのためには「離婚届」を作成して、市町村役場に提出しなければなりません。 しかし「離婚届をど ...
-

-
離婚前から離婚後にかけて行うべき諸手続きについて
結婚するときには「この人と一生を添い遂げよう」と決めても、さまざまな理由で旦那さまや奥さまと離婚せざるを得なくなるケースがあるものです。 しかし離婚の際には非常にたくさんの手続きが必要に ...
-

-
浮気の証拠になるものとは?効果的な集め方と使い方を完全解説!
夫や妻が浮気したら、何から始めたら良いのでしょうか? まずは「浮気の証拠」の収集を何より優先すべきです。 配偶者と離婚するにも復縁するにも、浮気の慰謝料請求を進めていくため ...